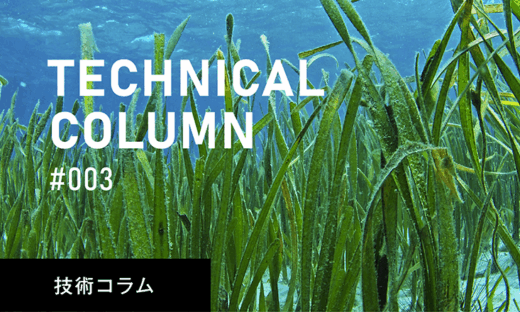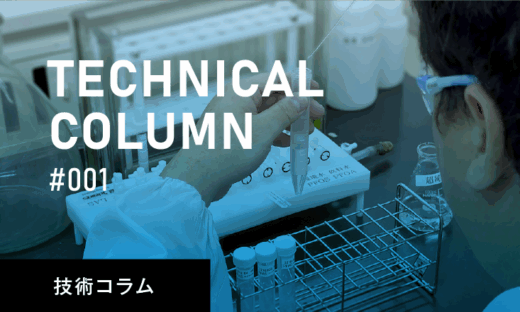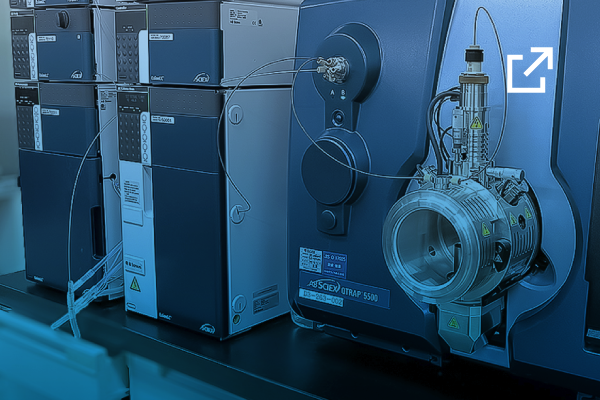ネイチャーポジティブに貢献するための行動

虫が嫌いな人が増えている? 自然体験と生物多様性のこれから
近年、年齢や性別を問わず「虫が苦手」という人が増えているようです。その背景には、都市化の進行があると考えられます。
自然の少ない環境で暮らしていると、昆虫と触れ合う機会はほとんどなく、日常で出会う虫といえば、家に入り込むゴキブリやハエ、蚊などの“害虫”ばかり。これでは、虫に対して良いイメージを持てなくて当然かもしれません。
メディアで取り上げられる昆虫も、スズメバチの巣の駆除やトコジラミの被害、外来種による影響など、ネガティブな話題が中心です。虫が「不快な存在」として印象づけられてしまうのも無理はありません。
こうした環境の中では、虫が嫌いな人にとって、害虫もそうでない虫もすべて「いなくなってほしい存在」になってしまいます。ましてや子どもの頃から昆虫に触れた経験がない人にとっては、昆虫の減少や生息地の消失といったニュースも、どこか遠い出来事に感じられるのではないでしょうか。
虫嫌いの大人は変われない? それなら子どもから
大人になってから虫嫌いを克服するのは、簡単なことではありません。ですが、子どもは違います。
幼いころから自然が身近にあり、虫がいる環境が当たり前になっていれば、多くの子どもは興味を持って接してくれます。
自然の中で昆虫や植物とふれ合うことは、生物多様性を肌で感じ、理解する第一歩。
将来、生物多様性を守る意識を持った人を育てるうえでも、都市部であっても子どもたちが自然に触れる機会をつくることは、とても大切になってきます。


都市の中の “身近な自然” を活用しよう
そんな中、注目されているのが「自然共生サイト」という取組みです。
これは、2030年までに生物多様性の保全地域を日本の陸地の30%に拡大する「30by30」目標の一環として、2023年からスタートした認定制度です。
2025年3月までに328か所、合計約9.3万ヘクタールが登録されました。
特徴的なのは、民間企業が所有する緑地や、これまで保全の対象になっていなかった都市部の雑木林、公園、ビオトープなども多数含まれていることです。
つまり、都市に住む子どもたちにとっても、身近な場所で自然と触れ合えるチャンスが広がっているのです。

都市部の子どもにこそ自然を
2050年に向けた国の予測では、地方の人口は大きく減少する一方、都市部には引き続き人が集中し、子どもの数は減りながらも “都市で暮らす子ども” の割合は高まるとされています。
つまり、これからの時代、自然体験の場を都市の中に確保することがますます重要になるのです。
2025年4月からは、「生物多様性増進活動促進法」が施行され、国・自治体・企業・NPO・個人などが連携して、生物多様性を “進める・回復する・創出する” 取組みを支援する仕組みもスタートしました。
自然共生サイトに多くの企業が参加している理由の一つに、環境への取組みをPRできることや、地域貢献によって従業員の満足度を高められるといったメリットがあります。
そして今後は、「子どもの自然体験の場」として活用することが、企業イメージや価値を高める新たな方法にもなっていくでしょう。
虫が好きな子どもを、もう一度都市から
「自然共生サイト」は、これまでの日本にはなかった “民間企業主導” の生物多様性保全の新たな形です。企業が所有する緑地を、地域の子どもたちが遊び、学び、虫や植物と触れ合う場所として開放していく。そうした環境が都市の中に増えていけば、虫が嫌いな子どもではなく、「虫が好きな子ども」がもう一度育っていくかもしれません。
行政では手が届きにくかったことを企業が担うことで、新しいかたちの社会貢献が実現する――。
これからの時代を生きる子どもたちのために、都市の中に自然を、そして昆虫との出会いを残していくことが、私たちの課題なのかもしれません。
関連するブログ記事をキーワードで探す
この記事の執筆者

菊原 久美
関東環境技術センター
1993年入社。主に自然環境調査や環境影響評価業務に従事。現地調査では動物分野を担当し、特に昆虫や魚類調査を得意としています。趣味は鳥の羽根集め。調査中で見つけると、ちょっと嬉しくなります。最近の目標は、いつまでも元気に現場で活動できる技術者でいること。そのために、日々、体力と気力の維持に努めています。